生物教科書のミステリー(3)
―進化論教育という犯罪―
進化論を政治的に利用
我々はジョナサン・ウエルズがIcons
of Evolutionで指摘した生物教科書の十項目ばかりの欺瞞のうち、特にヘッケルの胚の比較絵に焦点を絞って論じている。これが本人も認める偽造であり、いわゆる発生の反復説に全く根拠のないことが証明され、「一九二一年以来、いかなる真面
目な生物学者もこの反復説を用いたことがない」(モンタギュー)にもかかわらず、教科書がいまだにこれを載せ続けているのはなぜか。
ウエルズの新著Politically Incorrect Guide to Darwinism
and Intelligent Designにも指摘されているように、ダーウィン自身、化石の証拠が自説を支持するものではないことが次第に分かってきたので、この後輩の支持者のあみ出してくれた「個体発生は系統発生を繰り返す」説を頼みの綱としたのである。その意味でこれはいわば、ヘッケルとダーウィンの共謀によるものである。しかもこれはダーウィニズムの屋台骨であるから、何が何でも支え通
さなければならないものである。もしこれが倒れれば、持ちつ持たれつの関係にある、(これもヘッケルの手になる)あの「系統樹」と共倒れになり、ダーウィン進化論そのものが倒れなければならない。
私には学界のことは分からないが、想像するにこの反復説は、表向きは否定も肯定もされずにタブーとなっているのであろう。まともに肯定すれば常識を疑われる。まともに否定すればダーウィニズム専制体制からはじき出され、場合によっては職を失う。そして教科書はあたかもそっと糞を包むように、長年にわたって、これをそのまま次代へ次代へと手渡してきたのである。
このダーウィン=ヘッケリズムの悪質な欺瞞が、なぜ批判も受けずに(あるいは批判をかわして)これほど長く生き延びてきたのかについては、複合的な原因が考えられる。一つには、この教科書による洗脳教育そのものが功を奏してきたのであろう。誰にとっても教科書はほとんど神聖なものである。青年期にこの絵と「法則」を教え込まれた大多数の者は、普通
これを疑ってみたりはしない。幼児期に「将軍様」を救国の英雄と叩き込まれた北朝鮮人民は、そこから抜け出すのが我々が考えるほど容易ではなく、おそらくそのためにこの国家は予想以上に長持ちしているのである。
この欺瞞の犯罪性は計り知れない。胎児を魚のように見せかけるこの絵が、「何百万という無力な、生まれる前の子供たちの殺戮に対する、あるいは少なくとも、それに疑似科学的な根拠を与えたことに対する責任」(ヘンリー・モリス)だけでも、ダーウィニストには重いはずである。
エルンスト・ヘッケルという常習的偽造家は、いくつかの文献から判断する限り、生物学的な情熱から学問的にダーウィンに傾倒したわけでは全くない。それならある程度弁明の余地はあるであろう。そうではなく、「政治学とは応用生物学だ」という彼の言葉からもわかるように、彼は謀略家ともいうべき政治的イデオローグであり、ダーウィン進化論をそのために利用したに過ぎない。
人間と動物に差はない?
ここで前号に掲載した彼の主著の口絵を見ていただきたい。この絵の説明に当たるのがヘッケルの次の文章である(以下、引用はすべてRichard
Weikart, From Darwin to Hitlerからの借用である)――
最も高度に発達した動物の心と、最も発達していない人間の心との間には、ほんのわずかの量
的な違いがあるだけで、何ら質的な違いはない。そしてこの違いは、最も低い人間と最も高い人間の心の差よりもはるかに小さい。あるいは最も高い動物と最も低い動物の心の差よりも小さいと言ってよい。
これはダーウィン進化論から導き出される帰結である。要するに人間と動物(サル)との間には明確な一線がなく、血族的に連綿とつながっているのであって、この絵で言えば、6(最下等人間)と7(最高等サル)の違いは、1(最高等人間、白人=コーカソイド)と6との差よりもはるかに小さいと言っているのである。人間とサルの間の区切りは全く恣意的なものにすぎない。従って、1だけが人間、2以下はサル(あるいは異種)だと強弁することも、ダーウィニズムによれば可能である。
ダーウィンの考えた進化の進み方は、すべてが「徐々に少しずつ」「けじめなしに」ということであって断絶も飛躍も否定される。だから『種の起源』では、Natura
non facit saltum(自然は飛躍せず)というラテン語の諺が何度も引用され、またおそらく最もよく繰り返されるキーワードはincipient
species(種の発端となるもの)であって、ほんのわずかの親子の違いでも、長い間には全く別
の新しい種に変わり得るとする。つまり変種ができる以上、それは当然新しい種の創造にもつながるはずだという強弁であって、これはドーキンズなどにもそのまま受け継がれている。
人種差別の科学的根拠
ところで帝国主義、植民地争奪合戦の盛んだった二十世紀初頭のドイツやヨーロッパ列強は、人種差別
のための科学的根拠が喉から手が出るくらいに欲しかったに違いない。ダーウィン進化論はまさにその科学的根拠を与えるものであった。そして胎児の成長は、当然徐々に進むものであってそこに飛躍はないのだから、「個体発生は系統発生を繰り返す」という「法則」を仮定すれば、すべての動物に本来けじめがない(現在区別
があるのは溝が深まった状態にすぎない)というダーウィン説を確認したことになる。けじめがない代わりに、適応者と不適応者の勝敗による秩序だけが自然法則として残るのである。ヘッケルの活躍した当時のドイツにとって、ダーウィン進化論とこれを補強するヘッケルの反復説は、科学的証拠には全く関係なく、しかし「科学」として、社会的に必要だったのである。
もちろんこのような思想の持ち主はヘッケルだけではなかった。当時のドイツ知識人の言葉をいくつか挙げてみる。
[白人優越論]白人すなわちコーカサス人種は地球を支配するように定められている。これに対して、アメリカ人(先住民)、オーストラリア人(同)、Alfuren、ホッテントットといった最も低い人種は、大股に破滅へと向かいつつある。(Ludwig
Büchner)
[絶滅戦争の肯定]科学者は自然から正しい結論を引き出している。すなわち戦争、そして特に絶滅の戦争は――なぜなら自然界の戦争はすべてそれだから――自然の法則であり、それがなければ生物の世界はこのような状態になっていないだけでなく、全く存在を続けることもできないということだ。更に科学者はこの確信から一歩進んで、この普遍的な絶滅の戦いが有益な効果
を持つようにすることを、研究の目的としなければならない。(Gustav
Jaeger)
[スペインの南米原住民虐殺を弁護して]これこそが歴史の過程である。もし我々が地質学者の――そして現実にダーウィン理論を受け入れる地質学者の――目をもってこれを見るならば、この人間の種族の消滅ということは、かつて重要でない動物や植物が消滅したように、自然の過程なのである。(Oscar
Peschel)
こうした発言に我々は驚きあきれるが、当時としてはそれほどショッキングなものではなかったのであろう。ともあれ、当時の帝国主義とダーウィン進化論とが、いかに切り離せぬ
関係にあったかが分かるであろう。ワイカートの『ダーウィンからヒトラーへ――ドイツにおける進化論倫理、優生学、民族主義(人種差別
)』の中心人物がヘッケルであることはすでに述べたが、著者は結びにこう言っている――
ダーウィニズムそれ自体がホロコースト[ユダヤ人大虐殺]を生み出したわけではない。しかしダーウィニズム、特に社会ダーウィニズムや優生学というその変種がなければ、ヒトラーや彼のナチ追随者たちは、彼ら自身とその協力者たちに、あの世界最大の残虐行為の一つが、実際には道徳的に称揚されるべきものなのだと納得させるための、必要不可欠な科学的根拠を持つことはできなかったであろう。ダーウィニズム、あるいは少なくともダーウィニズムのある自然主義的解釈は、道徳を逆立ちさせることに成功したのである。
優生学とは、同一民族内での人種差別
(抹殺)に当たるもので、例えば劣等人間の強制的断種のような形で、当時のヨーロッパで真剣に考えられ論じられた方法である。次の引用はボン大学教授Ribbertの極端な優生学思想だが、これに近い考えをヘッケルも持っていたことをこの本は明らかにしている。
生まれて以来ずっと精神的にも肉体的にも役に立たず、自分自身にとっても重荷でしかない人間、何ら価値のない人間を養育することは、人類にとって全く無益な、実際のところむしろ有害な所業である。(Hugo
Ribbert)
恐るべき善なる思想
こうした二十世紀初頭のドイツ知識人の考え方は、我々には恐ろしいものとして感じられ、現に恐ろしい思想なのであるが、彼らは悪を勧めていたのでなく、むしろこれをダーウィン進化論という自然法則にかなった善なる思想として意識していたことを忘れてはならないだろう。Evolutionary
ethics(進化論倫理)という副題の言葉に明らかなように、彼らにとって善とは、進化の法則に従うこと、あるは進化の法則の実現に協力することであり、その進化とは、精神を持たぬ
、物質的な盲目的な力の自働作用であった。民族抹殺にせよ優生学にせよ、それは人類全体を向上させ、より健康体にするための、進化の法則にかなった方法であった。「健康」というのが(ニーチェの思想でもそうだが)、当時のドイツ思想界のキーワードであった。
こうした帝国主義者たちにとって、ダーウィン進化論は、証拠の有無にかかわらず、ヘッケルのうさん臭さにかかわらず、ともかくも「科学」であり「事実」でなければならなかった。それは社会的要請、国家的要請、更に言えば人類的――ただし白人をトップに置く人類秩序の――要請であって、批判してはならないものであった。またこれは、当時のヨーロッパ社会があえて批判する気にならないようなものでもあった。(もしかりにダーウィンやヘッケルが、日本人こそ世界を征服し支配すべき民族だと「科学的に」証明してくれたら、我々はあえてこれに異を唱えるだろうか?)
そして注目すべきは、こうしたダーウィン進化論成立にまつわる事情が、そのまま現在にまで尾を引いているということである。それはID理論の台頭によってはからずも明らかになった。ウエルズの新著にも明らかにされ、ネット情報を通
じても分かるように、ID派に対する体制派ダーウィニストの異常な敵意、ウエルズをして「ルイセンコ学説独裁下のソ連にそっくり」と言わしめる狂気じみた弾劾キャンペーンは、純粋な科学の世界で起こっていることとはとうてい思えない。いかさま師ヘッケルの偽造・捏造から始まった、科学でなく、無言の圧力としての――証拠の有無に関係なく「科学」であり「事実」でなければならないという――ダーウィニズムが、そのまま現在に引き継がれているのである。
話はこれくらいで終りにはならない。
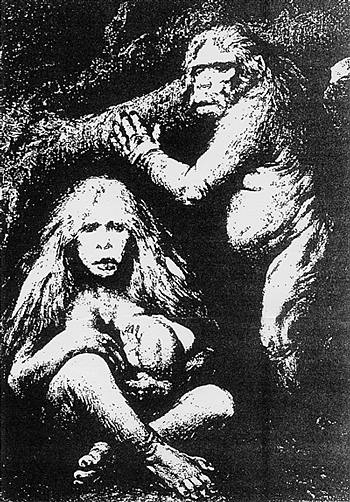 |
ヘッケルの偽造絵の一つ:――『創造の自然史』(1911版)に載せられており、人間とサルの中間動物だという。特に、坐っているメス(女)の足の形に注意せよ。
(Richard Weikart,From Darwin to Hitler,2005
より) |
『世界思想』No.373(2006年11月号)
|人間原理の探求INDES|前の論文|次の論文|